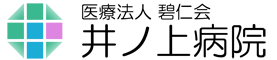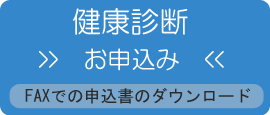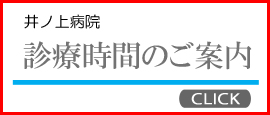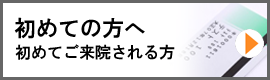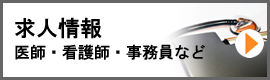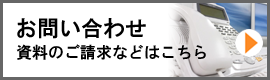外来では貧血の患者さんが結構います。
多くは鉄欠乏性貧血で鉄剤が処方されます。
腎臓でエリスロポイエチン(オリンピックなどで以前のドーピングの代表はエポでした、エリスロポイエチンのことです)合成がうまく働かない腎性貧血もあります。
さて、外来でよくお話しすることです。
「生卵は腐らないのにゆで卵は腐ります、どうしてでしょうか」。
さまざまな食物は熱をかけることで、細菌等を死滅させ安全な食べ物となります。ではどうして生卵は腐らないのでしょうか。
卵の白身にはオボトランスフェリンというタンパク質があり、これが鉄と結合しています。そのため白身にはフリーの鉄はほぼありません。
卵の殻はスカスカで細菌は自由に侵入できます、ただし白身にフリーの鉄がないため増殖することができません。そのため腐らないということになります。
一方、熱するとオボトランスフェリンの機能がなくなり、フリーの鉄が増えます。そのフリーの鉄を栄養分に細菌増殖が起こり腐るということになります。
この話のポイントは細菌感染にはフリーの鉄が必要であり、我々の体でも鉄のコントロールは厳密になされています。
鉄は赤血球の主要成分で重要であり、ほとんど排泄されず閉鎖系にあります。
ただし女性は月経で鉄を失います。
我々の血中ではトランスフェリンというタンパク質が鉄と結合しています。血中におけるフリーの鉄は10-18mol/Lとかなり低く、細菌感染を防御しています。
肝臓ではフェリチンというタンパク質が鉄と結合し、鉄の貯蔵庫となっています。
母乳にはラクトフェリンというタンパク質があり、これも鉄と結合しています。乳児はラクトフェリンを摂ることにより、感染症にかかることを避けているとも言えます。乳酸菌はあまり鉄を必要としない細菌です。乳児の初期の腸内細菌は乳酸菌など鉄を必要としない細菌が主体的で、そのためうんちに匂いがありません。ラクトフェリンの効果がなくなると、成人と同じことような腸内細菌叢となります。
さて、臨床の現場でのお話。
鉄欠乏性貧血の患者さんには、鉄剤の投与が頻繁に行われています。確かに鉄剤の投与で患者さんの症状は改善するかもしれませんが、同時にさまざまな感染症のリスクが出てくる可能性があります。
一つ例を。
結核などの慢性感染症では貧血がよく起こります。慢性的な炎症により血球生成能に障害が生じたためと説明されます。
専門的な話になりますが、ヘプシジンという鉄調節ペプチドが存在します。血中に鉄が増えるとヘプシジンが増え、鉄は肝臓に運ばれます。
逆に血中鉄が少ないとヘプシジンも減少します。慢性感染症において貧血が起こっていて、血中の鉄が少ない状態です。
そのような状態ですが、ヘプシジンは増加しています。このことをどのように解釈したらいいでしょうか。
慢性感染症があると、細菌等に鉄を利用させないために身体のメカニズムにより貧血を起こしていると考えるのが自然かと。
ところが臨床の現場では慢性感染症においては原因感染症の治療は当然ですが、貧血の治療することが多いようです。鉄剤投与により患者さんは元気になりますが、細菌はそれ以上に元気になります。
最後に生卵の話題をもう一つ。
生卵を食べるのはほぼ日本人だけということ知っていましたか。生卵が腐らないことはどこでも同じで、日本以外では衛生管理が悪くサルモネラ毒素が殻についていることが理由としてあげられます。
映画ロッキーシリーズの第一作で、ロッキー・バルボアがトレーニングの始まりに生卵5個飲むシーンがあります。日本人の私からすると気合入っているな、という印象でした。
でも、他の国の人たちにとっては衝撃的なシーンで、生命知らずの行為と印象付けられたことでしょう。