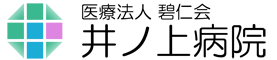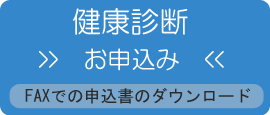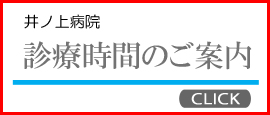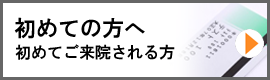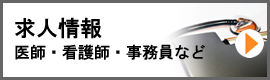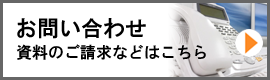外来診療では高血圧の患者さんが多いので、当然塩の話が多くなります。「血圧高いから塩分控えて」と当然のように医者は言いますが、話はそう簡単でなく少し込み入っています。今回は塩の話です。
昭和30年代の日本は脳卒中の国と言われていました。ここでの脳卒中は高血圧による脳出血と考えていいでしょう。ただしその頃血圧計はなく血圧は測定されていませんでした。
疫学研究によると北東北3県(青森、秋田、岩手)で特に頻度が高く、そこでの塩分摂取は1日あたり25gを超えていました。
一方、関西では塩の摂取量は少なく脳卒中頻度も低めでした。青森県の浪岡町(現青森市)では毎日りんごを食べる習慣があり、脳卒中の頻度は低いことも示されています。果物はカリウムを多く含み、カリウムはナトリウムと交換・排出することが知られています。塩は体液、血圧保持に絶対的に必要です、かつ高血圧と塩の関係は切ってもきれない関係です。
ではどのような食事を取ればいいのでしょう。
長年の研究成果をもとに米国からダッシュダイエットと言われる指針が出ています。
ダッシュ(DASH)とはDietary Approaches to Stop Hypertensionからきています。ナトリウム摂取を減らしカリウムを摂取すること、不飽和脂肪酸の多い植物性油を用いること、穀物は全粒穀物や玄米をとることなどで、日本人にとって塩分制限以外のハードルは低いかもしれません。ダッシュダイエットを2週間続けると血圧低下の効果があるそうですから、興味ある方は詳細を調べてみてください。最近の研究では代替食塩(NaCl 75%, KCl 25%)と食塩摂取の比較研究で脳卒中や新血管イベントが10%程度の減少が観察されたとのことです。代替食塩としては日本ではスーパーで「やさしお」として売られています。高くつきますが、血圧が心配な方は試してみたら良いでしょう。
趣向を変えて、塩が人類の歴史においてどれだけ重要であったかのお話ししましょう。
塩は全ての生物にとって生命維持に必要です。原生人類祖先(北京原人やジャワ原人は現生人類祖先ではないとされています)の一部は6-8万年前にアフリカを出て中東に移動します。そして中東で岩塩に出会います。アフリカでは岩塩はサハラ砂漠の中心部やエチオピア北部のアファール渓谷という海抜下の灼熱の地域にあり、どちらも人が住めるところではありません。人類は岩塩に出会うことで、チグリス・ユーフラテス川域のメソポタミア文明が生まれたと言って良いです。岩塩があったことで、まずは牧畜が始まります。野生動物を家畜化するには餌より塩が効果的です。
塩をおいておくと野生動物がやってきます。かつ家畜化には大量の塩が必要で、そこにも岩塩が使われます。文明前の話ですから、海水から大量の塩を得ることはできません。
人類は中東からヨーロッパ、東アジアへ移動します。東アジアへは南のルートと北のルートがあったようです。南ルートは暖かい地域の移動で食物も豊富だったことでしょう。北ルートは寒冷地で食物は少なかったことでしょうけど、なぜそのルートを取ったのでしょう。そこには岩塩がありました。牧畜しながら移動することが可能となります。そのルートはシルクロードとほぼ一致します。
我が国での塩の話になると、元禄時代に三河の吉良藩は海水からの製塩を行っていましたが、あまり質の良いものができなかったそうです。そこで良質な塩を作っている赤穂藩に製塩法の指導を請うたそうですが、拒否されています。塩に関しては吉良藩が赤穂藩のイジメに遭っていたと言えます。
このように吉良藩と赤穂藩では塩をめぐっての確執があり、松の廊下での刃傷沙汰につながったのかもしれません。当時、幕府は塩に税をかけていなかったので、赤穂藩は裕福でかなりの裏金を蓄えていました。赤穂藩は取り潰しとなりましたが、塩で得た資金は裏金だったので幕府に召し取られることはありませんでした。それが討ち入りの資金となったことは誰でも想像できることでしょう。裏金の使い勝手の良さは今も昔も変わりありません。
我が国では1905年に塩の専売が始まりました、日露戦争の戦費確保のためです、隠れた増税ですね。塩の専売は1997年に廃止され自由化されます。つい最近のことです。