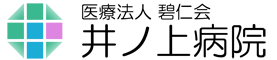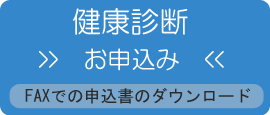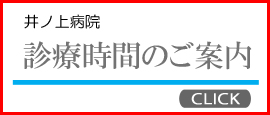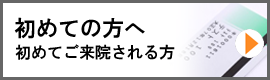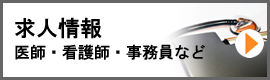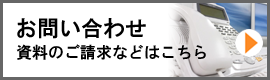新千円札の肖像に北里柴三郎博士が選ばれました。旧千円札は野口英世博士で、どちらも医学界の偉人です。
北里柴三郎は熊本県小熊郷北里村(現在の阿蘇郡小国町)で生まれ、熊本大学医学部の前身である西洋医学所から東京医学校(現東京大学医学部)へ進みます。教授に反発したこともあり、留年しつつも東京医学校を卒業し、内務省衛生局に入省し感染症研究を始めます。内務省には研究のため入省しただけで、権威にはことごとく反発した人でした。
特に東大医学部とは軋轢がありました。なにしろ北里は根っからの肥後もっこすですから。
そして北里はドイツのベルリン大学ロベルト・コッホ博士の研究室へ留学します。そこで、破傷風菌の培養に成功し、後にはペスト菌を発見します。
少し専門的ですが、破傷風菌が酸素を嫌う性質を見抜き、酸素のない状態(嫌気)での培養を行いました。これは嫌気性菌の発見でもあります。
そして「血清療法」の基礎を築き、現在では抗体療法としてがんなどの治療に用いられています。
同僚のエミール・フォン・ベーリングと共にジフテリアの血清療法を行い、ベーリングと共著で論文を出して、その業績が認められベーリングのみが第1回ノーベル医学生理学賞を受賞しています。
なぜ北里が受賞できなかったかには人種差別があったのではという説もありますが、当時、受賞者が一人に限られていたことが一番の要因のようです。第1回ですので、審査システムも確立していなかったと想像できます。
ノーベル賞受賞はならなかったものの、北里は一気にスーパースターとなり、アメリカやイギリスから高給での職のオファーがあったそうです。全て断って帰国することになります。
ただし、軋轢があった東大から声がかかることはなく、福沢諭吉(こちらもお札の肖像です)の私的支援により私立伝染病研究所を設立します。
当初は東京の芝公園、そして愛宕に場所が移り、その後、伝染病研究所は内務省管轄の国立となり白金台に移ります。手狭だったこと、感染症研究として都心は相応しくなかったことなどが理由でしょう。
私自身も所属していた東京大学医科学研究所の前身です。
そのうちに、国の方針で伝染病研究所が文部省管轄となり、東大の下部組織となりました。北里はそれに反発して研究所所長を辞めています。
そして自分で開設していた結核療養所があった白金に北里研究所を設立します。白金は白金台の隣になります。
現在はそこに北里大学薬学部や北里研究所病院があります。
伝染病研究所を辞してすぐ近くに研究所を設立するとは反骨精神の溢れる北里らしいところです。肥後もっこす所以たるものでしょう。
東大とは脚気論争でも揉めました。病気の原因として細菌が関与していることがわからなかった時代です。
その頃、軍では脚気による心臓疾患での死亡が問題となっており、脚気の原因について論争がありました。
東大の恩師が脚気菌を発見したとする論文が出しましたが、北里は実験手法を批判します。実験への真摯な姿勢があったのでしょうが、東大という権威への反発もあったかと。結果、恩義のない者と非難されます、その先鋒の一人が森 林太郎(作家名:鴎外)でした。
脚気の原因をめぐり、陸軍軍医の森 林太郎と海軍軍医の高木兼寛の争いがありました。高木兼寛により脚気は細菌によるものではなくビタミンB1不足と証明され、海軍では脚気は一掃されます。
高木兼寛は日向国諸県郡穆佐郷(現在の宮崎市)生まれの薩摩藩士で、東京慈恵医科大学を創設します。
ちなみに鹿児島医学校に入学し、その後、教授となっていますので、私の先輩に当たります。
北里は伝染病研究所を辞めた後も、日本の医学のために尽くしました。
まず慶應大学医学部の初代医学部長に就任しています。そして日本医学会を立ち上げ初代副会長となり、日本医師会の初代会長でもあります。
研究者として際立った研究業績を残しただけでなく、行政的な手腕もあり、日本の医学会の発展に尽くした姿勢、能力は医学、医療に身をよせるものとしては尊敬しかありません。
実際のところ、東大という当時の絶対的な権威に反発しながらも、医学界に大きな足跡を残せたことは驚きでしかありません。福沢諭吉という後ろ盾がありました、それも北里がそれだけの人物であったからでしょう。
留学先師匠のコッホには尊敬の念が強かったようで、白金の北里大学キャンパスにはコッホ・北里神社があります。そこにはコッホ祠があります。外国人を祀った神社が他にあるのでしょうか。
最後に旧千円札の野口英世についても少しだけ触れます。彼は病原体としての細菌発見に尽力した人です。彼が発見したという病原細菌ですが、多くはウイルスを原因とすることがわかっており、彼のほとんどの研究は否定されています。ガーナのアクラで黄熱病研究中、黄熱病で死亡します。
なおアクラには野口記念医学研究所があり、私が所属していた国立遺伝学研究所とは共同研究契約を締結しております。