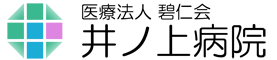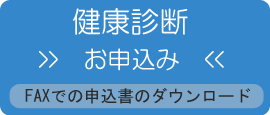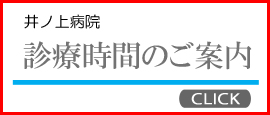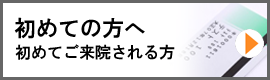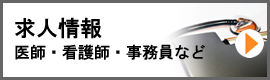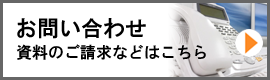時間が経ってしまいましたが、その1からの続きです。
私は肝臓で発現する遺伝子の研究に少しだけ従事していました。
ヒト肝臓組織があれば、そこで発現する遺伝子を網羅的に検出できます。遺伝子からタンパクができますので、増えたり減ったりしているタンパク質を知ることができるといってもいいです。
シトリン血症という遺伝病の研究で、患者肝臓で特異的な遺伝子発現を見つける仕事です。シトリン血症は私の恩師である鹿児島大学前教授の佐伯武頼先生が長年研究された病気です。
シトリン血症では加速した形で脂肪肝、脂肪肝炎、肝硬変、肝がんへと進行します。シトリン血症の患者肝臓ではPPARα(中性脂肪代謝に重要なタンパク質)発現が著明に低下していました。肝臓において中性脂肪を代謝できない状態といえます。
遺伝病と一般的な脂肪肝を一緒にはできませんが、PPARαを活性化する薬が脂肪肝に効果あるのではと考えるもう一つの理由です。
最近の脂肪肝の話(その1)で脂肪肝から脂肪肝炎、肝硬変、肝がんと進行すると申しました。
実際のところ脂肪肝の状態で止まっていると健康上の問題は大したことありません。繊維化や炎症がおこり脂肪肝炎となると、様々な症状が出てきます。
しかしながら、脂肪肝から脂肪肝炎への進行を知ることは簡単ではなく、肝臓の生検で確認します。侵襲的な診断法ですので、当然リスクを伴いますし、開業医レベルではできることではありません。
最近ではFibroScanといった画像診断の手法もあるようですが、一定の結果は得られないようです。
血液検査でわかればいいのですが、ALT,AST,γGTPといったよく使われる肝臓マーカーでは肝炎への進行を知ることは困難です。
肝臓学会が勧めているFib-4は肝硬変に至る重症例にしか適用できないようです。NASH, MASHの概念的がない頃に提唱されたものですから仕方ありません。
最近、Cell Metabolismという一流誌に掲載された論文のことを少しだけ。
論文では脂肪肝、脂肪肝炎を鑑別診断するモデルが発表されています。詳細は省きますが、これまでも脂肪肝炎のマーカーとして使われていたサイトケラチン(CK-18)に加え、血液中に存在する炎症関連のタンパク質、そして肥満度(BMI)に注目し診断モデルを構築しています。
脂肪肝と脂肪肝炎を鑑別診断できることに加え、どのような脂肪肝が進行して脂肪肝炎になるかを示しています。
脂肪肝、脂肪肝炎が炎症疾患であることを改めて認識させられます。脂肪肝の治療としてビタミンEが用いられますが、抗酸化作用を期待してのことで、理屈は通っているのかもしれません。
付け加えておきますが、論文が出たからといって、それが普遍性を持つかは別な話です。臨床の現場で使われるには時間がかかります。
今回は飲酒を主因としない脂肪肝の話でした。
次は飲酒による脂肪肝の話にしましょうか。
お酒を大量に飲むと脂肪肝になる、当たり前のようですが、メカニズムとなると若干込み入った話です。専門的な内容にならないようお伝えできたらと思います。
【参考文献】
Zhang et al., 2025, Cell Metabolism 37, 1–10